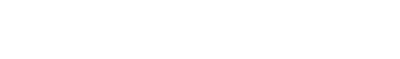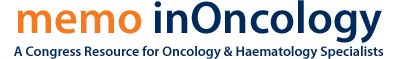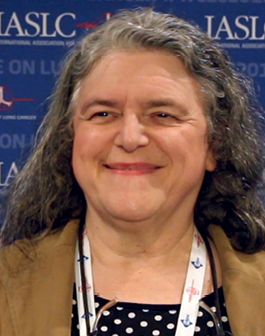巻頭言
Vera Hirsh, MD カナダ・モントリオール マギル大学ヘルスセンター 腫瘍内科
臨床医の皆様へ
転帰を改善しようと私たちが努力を重ねるうちに、肺がん治療への要求も変化してきている。できる限り良い形で延命させるための抗がん剤使用を探る以外に、毒性をどうコントロールするかを学び、医療保険制度に負担がかからないよう長期的に医療費を抑える方策を見つけなければならない。2018年9月23日から26日までカナダ・トロントで行われた第19回世界肺癌学会議で発表された臨床試験データからは、進行期の小細胞肺がん患者への化学療法にアテゾリズマブを追加した場合の生存期間の延長といった、一歩大きく前進する知見が報告された。 進行期の小細胞肺がん患者への現行の標準的ファーストライン治療で、20年以上ぶりに生存率の改善に臨床的意義が見られた初の臨床試験である。
切除が不可能なⅢ期の非小細胞肺がんの症例にデュルバルマブを投与した場合でも、生存率や生存期間に大幅な改善が見られた。ALK融合遺伝子陽性肺がん患者に、次世代のCNS活性型ALK阻害薬ブリガチニブをファーストライン投与した際、その効果が認められた。肺がん遺伝子のドライバー変異が多岐にわたるということは、これらが分子標的薬のターゲットであることを表している。このことを勘案すれば、かなりの割合の末期肺がん患者を治療できるようになる、ということだ。説得力のあるデータが非常に限られていたため、議論されることのなかった肺がん検診について、期待を抱かせる新たなデータが最後に報告されている。ボリュームCTによる検診を行うことで、男女とも肺がんの死亡率が著しく低下している。
しかし、進行肺がんに限定した場合、治癒に至るのはわずか2%の患者であり、患者数の多いこのがんにとって治療は基本的に緩和目的になることを意味している。生活の質はすべての面につながっているのでこの点にはしっかりと注意をし、日々の看護で軽視してはならない。治療を受けないでいるよりそれを受けることで、患者の寿命をただ延ばすのではなく、より良い毎日を送ってもらえるようにできるかどうかは、医療従事者である私たちにかかっている。患者の視点はどんな検査所見や画像所見よりも大切である。とはいえ、こういう所見も大切であることに変わりはないのだが。生活の質を迅速かつ効果的に評価できるツールや患者報告アウトカムのツールが考案されている。これらの結果からは患者のニーズをかなり知ることができるだけでなく、各患者の予後を驚くほど正確に把握することもできる。それぞれの患者に既存の手段を包括的に用いることで、深刻な病状であっても希望を与え、充実した時を過ごしてもらえるきっかけになるだろう。
More posts
患者の見解:生活の質の評価と肺がんに関わるスティグマ
患者の見解:生活の質の評価と肺がんに関わるスティグマ 肺がんによる負担 生活の質(QoL)評価は患者に大変重要視されていて、肺がん治療の評価に欠かせない要素ではあるが、日常
肺がん検診にボリュームCTを用いることで肺がんの死亡率が大幅に低下:NELSON試験
肺がん検診にボリュームCTを用いることで肺がんの死亡率が大幅に低下:NELSON試験 2011年に発表のあった全米肺がん検診試験(NLST)からは、3年にわたり低線量CTを
インタビュー:第I相試験であっても新薬には劇的な効果が見られる
第I相試験であっても新薬には劇的な効果が見られる Herbert Ho Fung Loong, MD中国、香港中文大学、一期臨床研究中心、臨床腫瘍科次長、臨床准教授 現時
抗EGFR抗体薬:実臨床での使用経験と治験で得た感想
抗EGFR抗体薬:実臨床での使用経験と治験で得た感想 治療の選択肢を決めるのはそれぞれの因子 ⅢB期・Ⅳ期のEGFR遺伝子変異NSCLCへの治療法がここ数年の間に大きく変わ
まれなドライバー遺伝子変異のある腫瘍への新しい標準治療
まれなドライバー遺伝子変異のある腫瘍への新しい標準治療 ファーストライン治療のブリガチニブ:ALTA-1L試験 ALK陽性NSCLCの治療におけるファーストラインの標準治療
免疫療法を受ける患者の転帰への抗PD-L1抗体薬の活性および決定因子に関する新データ
免疫療法を受ける患者の転帰への抗PD-L1抗体薬の活性および決定因子に関する新データ PACIFIC試験ではデュルバルマブ群の生存率が優位に 切除が不可能なⅢ期の非小細胞肺