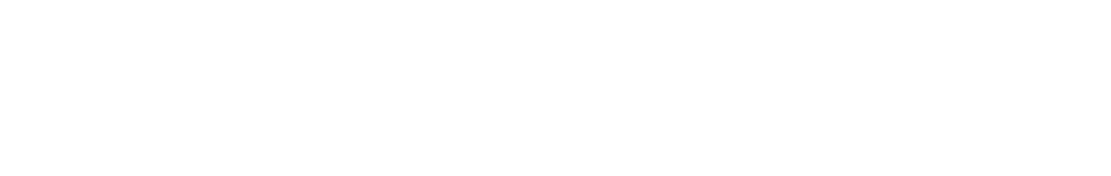肺がん検診:普段の検診や研究室にとっての課題

Luis M. Montuenga, PhD, Centro de Investigaci溶 M仕ica Aplicada (CIMA); Department of Pathology, Anatomy and Physiology, Schools of Medicine and Sciences; University of Navarra, Pamplona, Spain. IdisNa, Pamplona Spain. CIBERONC, Madrid, Spain
低線量肺がんCT検診が世界的にいまひとつ普及しない原因は何だとお思いになりますか。
低線量CT(LDCT)には効果があり、広く利用するべきだという考えに異を唱える人はいないでしょう。どの国でも費用と認識不足の2つがLDCTの実施の足かせになっていると思います。 LDCTの費用対効果については多くの文献で示されていますし、費用対効果の高さに軍配を上げる文献もあります。肺がん検診に利用していますが、その際に(冠動脈石灰化スコアに基づいて)心疾患や肺気腫といった他の疾患も同時に発見することができます。低線量肺がんCT検診が長年にわたって物議を醸していることが、おそらく認識不足につながっているのだと思います。物議を醸したというところがまだ引っかかっているのでしょうが、全米肺がん検診試験(NLST)や他の診断基準に該当する患者さんへの検診にLDCTを利用することの有用性が、最近のエビデンスではっきりと示されています[1~3]。肺がんに悪いイメージがあることも、LDCTの利用がいまひとつ広まらない理由なのかもしれません。
新規バイオマーカーが肺がん検診の精度をどう向上させられるのでしょう。
まず、バイオマーカーを2つのコンセプトで分けないといけません。一つは、肺がんの診断後に患者さんの転帰を予測するのに利用できるバイオマーカーです。世界肺癌学会(IASLC)のstaging committee(病期分類に関わる委員会)には、予後予測に利用できるバイオマーカーを特定して、TNM分類の有効性を改善することを専門にしている分科会があります。私が所属する研究室でも、早期肺がんを予測できるバイオマーカーの特定に取り組んでいます。
もう一つは、低線量肺がんCT検診に役立てられるバイオマーカーです。まず、スクリーニングプログラムに参加してもらいたい高リスク患者を見つけやすくなる可能性があります。すでに使われているリスクモデルの精度が、このバイオマーカーで高められるかもしれません。遺伝子バイオマーカーや、環境暴露や喫煙習慣を基にしたバイオマーカー以外に、ctDNAもあります。また、肺がん検診に役立てられるバイオマーカーには、良性と悪性の鑑別が困難な肺結節の判断に利用できる面もあります。明らかに良性の肺結節も、間違いなく悪性ですぐに治療が必要な結節もLDCTは検出しますが、症例のおよそ70%では、肺結節の悪性リスクをはっきりと判定できません。このような場合、バイオマーカーによってリスク層別化のレベルが向上するので、結果的にPET検査や生検など 不必要な検査をしなくてすむようになります。
肺がんの早期発見という点ではどのバイオマーカーを有望視していますか。
数が多いので絞るのが難しいですね。バイオマーカーを発見したという文献は本当にたくさんありまして、自己抗体、血中タンパク質のプロファイル、補体分解産物、マイクロRNA、血中遊離メチル化DNA、気道や鼻腔で採取した検体のRNAの特徴といった候補に期待しています[4]。あと、呼気バイオマーカー、メタボロミクス、喀痰細胞診、遺伝的素因、次世代シーケンシングによる血液腫瘍循環DNAの検出といった新規のバイオマーカーや新技術もあります。
ただ、どれも臨床的有用性を検証する必要があるのですが、この検証が一番の問題になっています。新規バイオマーカーが検証の段階までこぎつければ、その後に期待できますが、肺がん検診に活用できそうなもので、この段階に至ったものはまだありません。いくつかのバイオマーカーに臨床試験である種の検証をしておりまして、検診を受けた患者コホートから採取した検体を用いる対照試験などがその一例です。ですが、バイオマーカーが高リスク患者さんや肺がん検診でリスクの程度を特定できなかった患者さんの治療管理に役立ったり、治療管理を改善させたりすることが確認できるように臨床試験をデザインするのが筋だと思います。そうは言っても生体試料を採取しているスクリーニングプログラム自体が少ないので、この問題が簡単に解決するとは思えませんし、すべてのスクリーニングプログラムが協力しあうことや、手順の標準化、試験デザインの改善も必要です。こういった一連の工程を経ることでどのバイオマーカーが有望なのかがわかります。現時点では幅広い領域に利用できるバイオマーカーが市場に出回っていますが、肺がん検診に利活用することで標準治療の効果を上げられるものを発見するのが最重要課題だと思います。
参考文献:
- Aberle DR et al., Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med 2011; 365(5): 395-409
- Henschke CI et al., CT screening for lung cancer: significance of diagnoses in its baseline cycle. Clin Imaging 2006; 30(1): 11-15
- Yousaf-Khan U et al., Final screening round of the NELSON lung cancer screening trial: The effect of a 2.5-year screening interval. Thorax 2017; 72(1): 48-56
- Seijo LM et al., Biomarkers in lung cancer screening: achievements, promises and challenges. J Thorac Oncol 2019; 14(3): 343-357
© 2020 Springer-Verlag GmbH, Impressum
More posts
KRAS・HER2・ALKの各遺伝子の阻害薬と使用する治療ラインの問題点
KRAS p.G12C変異は肺がん患者の約13%に生じるがん関連の主要な遺伝子変異で、転帰不良の一因にもなっている。極めて選択性が高いKRASG12Cの画期的な不可逆的阻害薬であるソトラシブが、第Ⅰ相CodeBreaK 100試験に参加した、前治療歴の多いNSCLC患者コホート59人にしっかりとした臨床的有用性を示した。 本学会では、申請のもとになる第Ⅱ相オープンラベル単群試験の対象になったNSCLC患者コホートに関する成績をLiらが発表した 。
早期肺がんの範囲を広げる
非小細胞肺がん(NSCLC)患者のおよそ30%は、診断を受けた時点で切除可能な段階にある。この場合は根治手術が推奨療法となり、術後はⅡ期・ⅢA期の患者とIB期の一部の患者にはシスプラチンベースのアジュバント化学療法を行っているが、アジュバント化学療法の実施状態に関わらずどのステージでも再発率は高止まりしている。NSCLCを完全切除したIB期からⅢA期の患者を対象にした第Ⅲ相二重盲検ランダム化比較ADAURA試験で、第三世代のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬(TKI)・オシメルチニブを術後に投与した群で無病生存期間(DFS)に統計学的有意かつ臨床的意義のある延長効果(HR:0.20、p<0.0001)が認められた。
巻頭言
2020年度世界肺癌学会(WCLC)は当初、昨年の8月にシンガポールで開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界中に蔓延したため今年1月に延期となり、同月28日から31日にかけて何とかバーチャル会議を開催することができました。肺がんをはじめ胸部悪性腫瘍領域の科学者・研究者・患者支援団体が一堂に会する、世界有数の会議であるWCLCは今回も参加者同士を結びつけ、研究や治療法についての最新の知識や知見を互いに分かち合って学ぶ、絶好の場になりました。